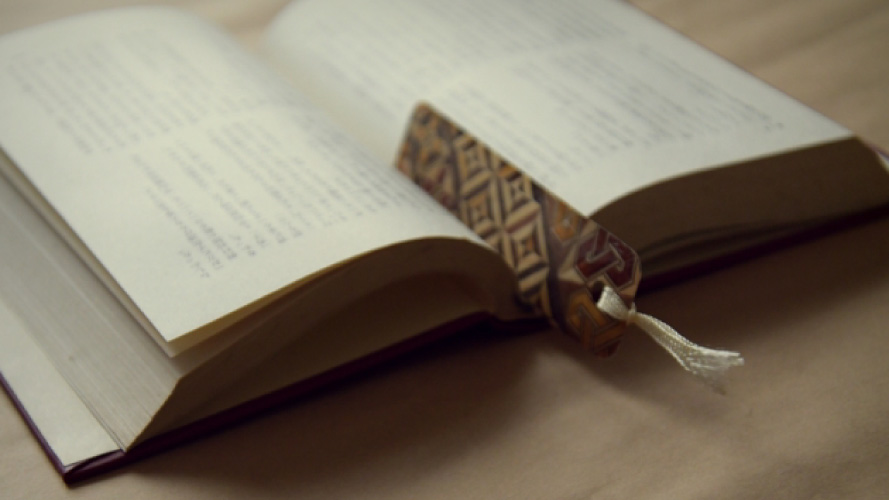 特集
特集 経営事項審査で建設業経理士の加点を得るには講習が必須に
SATO行政書士法人から建設業の経営事項審査に関する改正情報を共有いたします。 これまで、建設業の経理事務士の2級以上の資格を持っている方は、加点対象となっていましたが、今年の4月からは、資格取得後5...
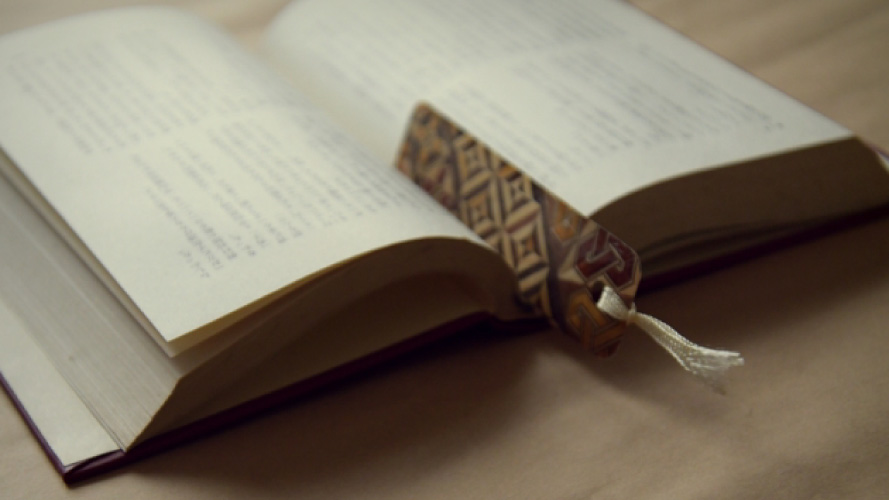 特集
特集  ニュース
ニュース  ニュース
ニュース  お知らせ
お知らせ  ニュース
ニュース 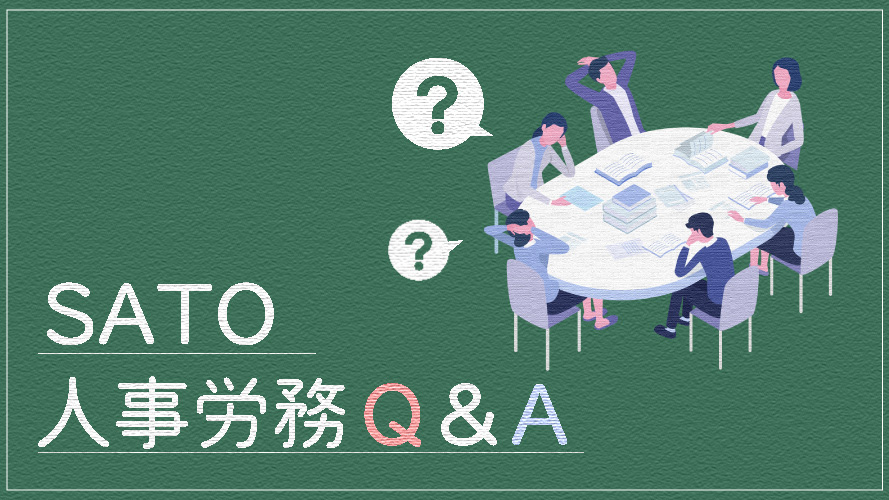 Q&A
Q&A 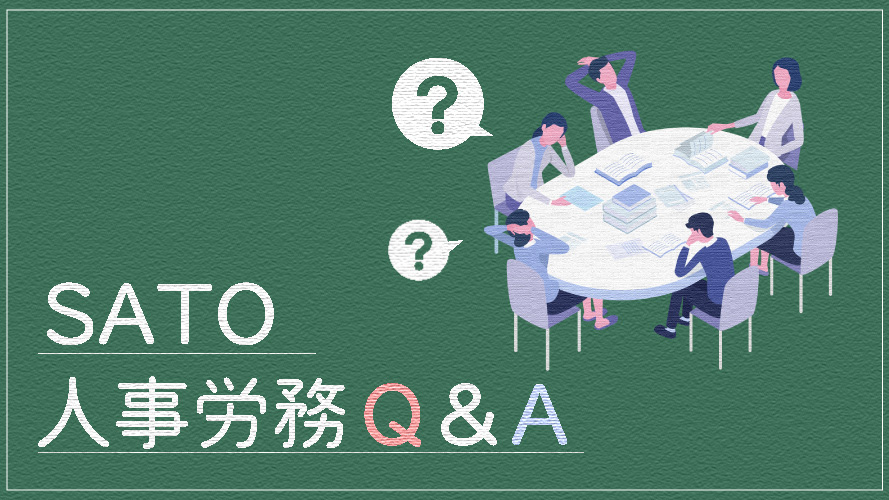 Q&A
Q&A 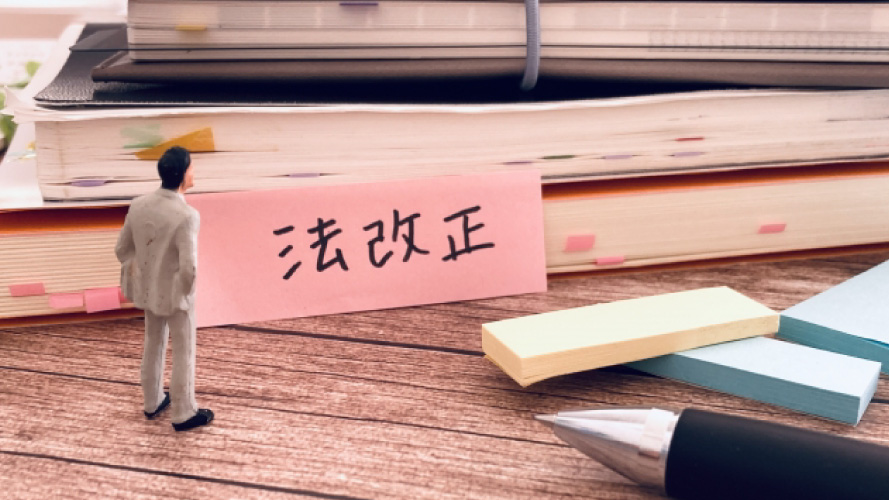 ニュース
ニュース 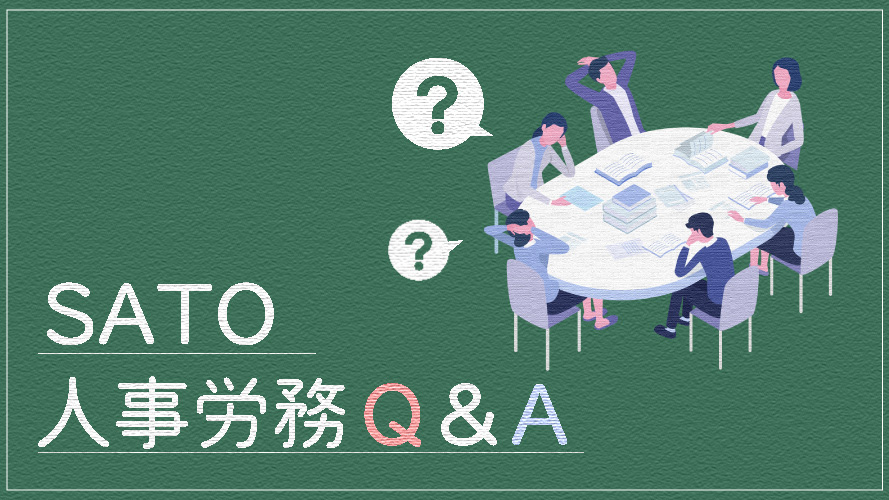 Q&A
Q&A  特集
特集  特集
特集  ニュース
ニュース 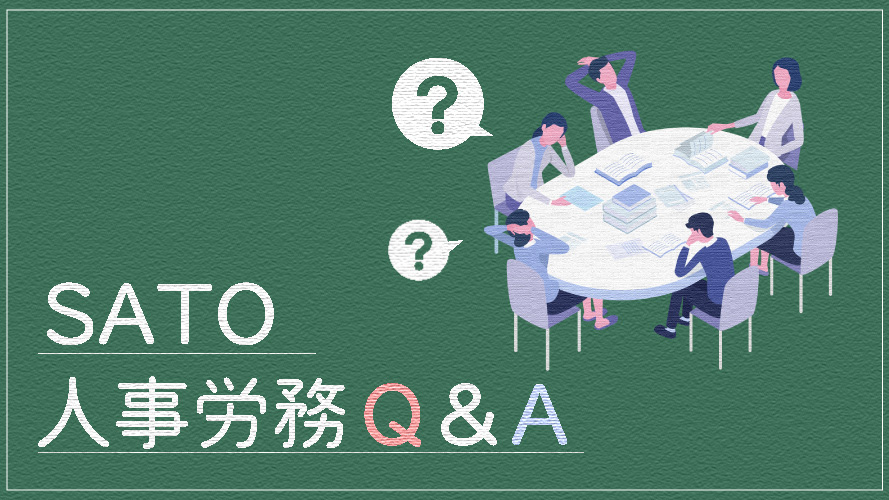 Q&A
Q&A 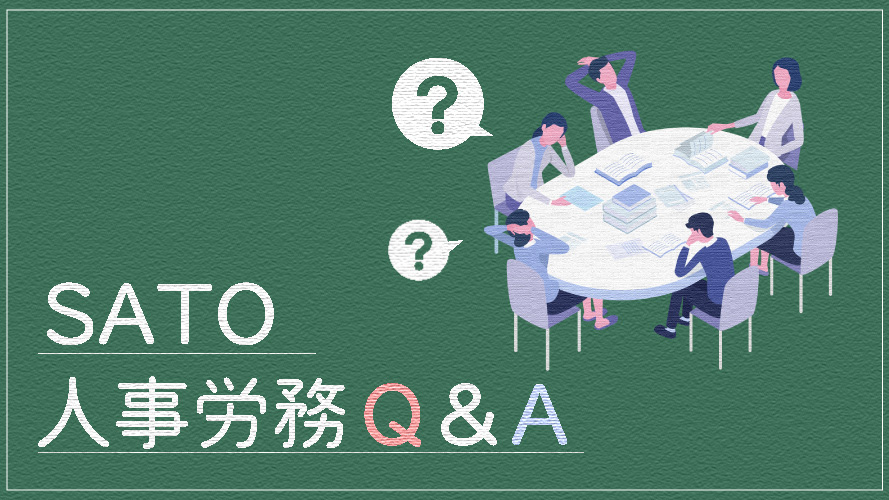 Q&A
Q&A 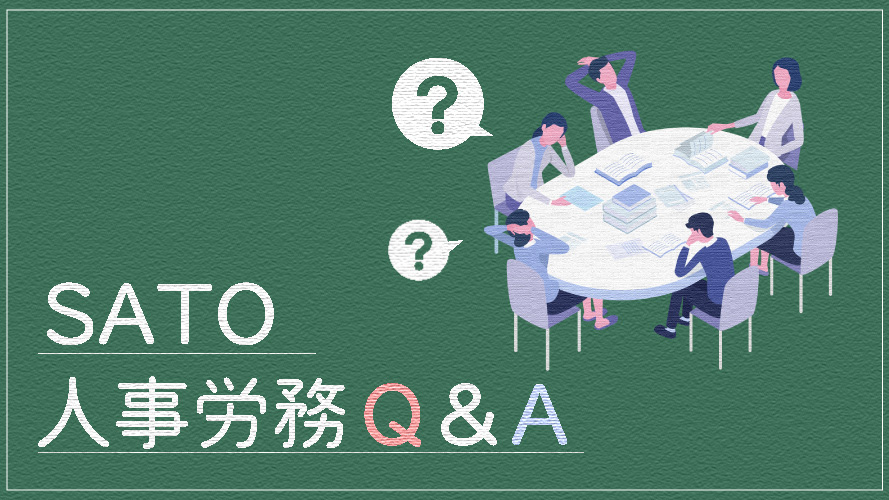 Q&A
Q&A